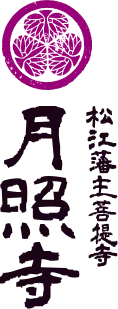建築
時を超えて息づく
江戸建築の粋
名工たちの精緻な技が結晶した月照寺の建築群。
廟所や寺門をはじめとする建造物が、
歴代の松江藩主とともに時を超え、
当時の風格を今に伝えています。
それぞれの建築には、歴史や逸話が宿り、
訪れる人々に往時の面影を感じさせます。





書院
現在の書院は、国際文化観光都市・松江の藩主菩提寺としてふさわしいものを目指し、昭和59年に改築されました。
右奥には「御成りの間」があり、安土桃山時代の遺風を伝える書院造りが再現されています。
一般公開されており、希望すれば郷土作家による茶器でお茶を楽しむこともできます。


御霊屋
寛政10年(1798年)に建築された歴代藩主の位牌を安置する建物です。
総造りで仕上げられ、内部の壁画は狩野永雲の筆によるもの。
毎年8月16日限定の「御霊屋開き」に開扉され、一般の参拝を受け付けます。




現本堂
昭和29年に建立された本堂。
ご本尊の阿弥陀如来像は、初代藩主・松平直政公が月照院の冥福を祈って造立したものです。
堂内には狩野永雲筆の十六羅漢が掲げられ、外の額には十代藩主・定安公の筆が残されています。



茶室・大圓庵
現本堂の奥に位置し、静かに佇む茶室。
かつては茶の湯が行われていた場所であり、往時の雰囲気を今に伝えています。
歴代藩主が愛した茶道の伝統を感じることができる空間となっています。

宝物殿
松江藩主ゆかりの貴重な品々を収蔵・展示している宝物殿。
不昧公像や超特大涅槃図など、他では見られない貴重な文化財が数多く収められています。

唐門
17世紀中期の建築と推定される一間一戸の平唐門。
彫刻の形状から松江藩の御作事所による建築と考えられています。
旧圓流寺(松江市西尾町)から移築されたという説もありますが、詳細は定かではありません。



鐘楼
17世紀中期に建築されたと推定される鐘楼。
象鼻の装飾が施されており、松江藩の御作事所による建築と考えられます。
大正時代の境内整備の際に現在の位置へ移されました。





初代直政公墓所
延宝7年(1679年)に建築された松平直政公の廟所。
廟門は島根県指定文化財で、軒唐破風には虎と竹の精巧な彫刻が施され、格式の高さを感じさせます。
松江藩の初代藩主である直政公は、徳川家康の孫にあたり、武勇に優れた人物でした。
大阪の陣で活躍し、真田幸村からその戦いぶりを称賛された逸話も残っています。
また、藩政においても日御碕神社や出雲大社の造営を手掛け、信仰を重んじた名君として知られます。
寛文6年(1666年)、江戸藩邸で没しました。





二代綱隆公墓所
延宝4年(1676年)に建築された廟所。
軒唐破風には桐紋の彫刻が施され、格式を持ちながらも初代直政公の廟門よりもやや簡素な造りとなっています。
綱隆公は文芸に秀で、特に絵画の才能が高く、狩野永雲に学び多くの作品を残しました。
また、松江藩の菩提寺として月照寺を正式に定め、整備を進めた人物でもあります。
延宝3年(1675年)、44歳で急逝しました。





三代綱近公墓所
宝永7年(1710年)に建築された廟所。
桁行一間、梁間一間、切妻造で、軒唐破風には龍の彫刻が施されています。
綱近公は17歳で家督を継ぎ、藩政の安定に尽力しました。
農業政策を推進し、漆や桑、楮などの栽培を奨励。
また、古志原を開拓し、後に薬用人参の栽培地として活用される基盤を作りました。
しかし、度重なる水害や藩財政の困難にも直面しました。
失明後は牡丹を愛し、香りを楽しむことで心を慰めていたと伝えられています。
宝永6年(1709年)、51歳で没しました。





四代吉透公墓所
宝永4年(1707年)に建築された廟所。
向唐門の構造を持ち、蟇股には六つ葵や桐紋の彫刻が施されています。
吉透公は兄・綱近公の後を継ぎ、宝永元年(1704年)に藩主となりましたが、翌年には病で江戸にて急逝しました。
治世は短かったものの、松江藩の安定を図り、父や兄が進めた藩政を引き継ぐ役割を担いました。
宝永2年(1705年)、38歳で没しました。





五代宣維公墓所
享保16年(1731年)に建築された廟所。
水鳥や象鼻の彫刻が施され、高度な大工技術を示しています。
宣維公は宝永2年(1705年)に8歳で藩主となり、数々の天災や外敵の脅威に対応しました。
特に美保関周辺への外国船の出没が続き、幕府の許可を得て砲撃を実施するなど、防備の強化に努めました。
享保5年(1720年)には隠岐の統治を再開し、藩の防衛体制を整備しました。
享保16年(1731年)、34歳で没しました。





六代宗衍公墓所
没後に建築されたと推定される廟所。
象鼻や仁王像の浮彫が施され、五代宣維公の廟門と同じ構造を持っています。
宗衍公は享保14年(1729年)に生まれ、16歳で藩主となりました。
当時、松江藩は深刻な財政難に直面しており、「延享の改革」と呼ばれる経済政策を実施。藩営金融機関や産業振興策を導入し、経済の活性化を図りました。
しかし、幕府からの大規模な工事命令が財政に大きな負担を与え、改革は挫折。
晩年は江戸に隠棲し、松江に戻ることなく天明2年(1782年)、54歳で没しました。





七代治郷公墓所
文政7年(1819年)に建築された廟所。
廟門は島根県指定文化財で、頭貫には葡萄の彫刻が施され、小林如泥の作と伝えられています。
治郷公は宝暦元年(1751年)に生まれ、17歳で藩主となりました。
茶道に精通し、「不昧流茶道」を確立。
不昧公として名を残し、茶の湯文化の発展に貢献しました。
また、藩政においても倹約令を施行し、藩財政の立て直しを図りました。
文政元年(1818年)、68歳で江戸・大崎にて没しました。





八代斉恒公墓所
文政6年(1823年)に建築された廟所。
牡丹や瓢箪、栗鼠、唐獅子などの彫刻が施され、華やかな意匠が特徴です。
斉恒公は文化3年(1806年)に生まれ、16歳で藩主となりました。
治郷公の影響を受け、茶道や書に優れ、瓢庵月潭と号しました。
また、外国船の隠岐出没に対応するため、軍備の増強にも努めました。
文政5年(1822年)、32歳で没しました。





九代斉斎公墓所
没後に建築されたと推定される廟所。
妻面の虹梁上部前面には松に鷹の透かし彫りが施されており、鷹狩を好んだ斉斎公の趣向が反映されています。
文化12年(1815年)に生まれ、文政5年(1822年)に藩主となりました。
藩政においては『出雲版延喜式』を完成させ、幕命により『南史』百巻を校刻するなど、文化事業にも貢献。
土木事業にも力を入れ、簸川郡の新川工事を進めました。
西洋文化にも関心を持つ一方で、粟飯や風呂吹大根を好んだという逸話も残っています。
文久3年(1863年)、49歳で没しました。





異形五輪塔
初代・五代・六代・七代・九代藩主の墓所に建てられている異形五輪塔。
通常の五輪塔とは異なり、独特な形状を持つ石塔です。
松江藩主の墓所を象徴する存在であり、藩主たちの信仰や権威を建立当時のままの姿で現存しています。




五輪塔
二代・三代・四代・八代藩主の墓所には、伝統的な五輪塔が建てられています。
五輪塔は、仏教の「地・水・火・風・空」の五大要素を象徴する石塔であり、藩主たちの冥福を祈るために建立されました。
松江藩主の墓所を象徴する存在であり、藩主たちの信仰や権威を今に伝えています。