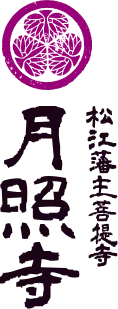大亀像について
月照寺の境内に静かに佇む、
大きな石造の大亀像。
長寿祈願のご利益があるとされ、
多くの方が願いを託してきました。
近年では、朝ドラで取り上げられた
小泉八雲と妻・セツのゆかりの地としても
注目を集めています。
長い時を越えて親しまれてきたこの大亀像は、
月照寺を象徴する存在として、
今も多くの人々を見守り続けています。
大亀像とは
松江藩主・松平家七代治郷公(不昧公)は、
父・宗衍公の願いを受け、
その徳を讃え寿命長久を祈るために
「寿蔵碑(生前供養塔)」を建立しました。

石材は天明元年(1781年)、松江から二十数キロ離れた出雲市久多見町の山中で切り出され、宍道湖を舟や筏で運ばれたと伝えられています。
石碑は翌年に完成しましたが、宗衍公の逝去の日までに建てられたかどうかは定かではありません。
この寿蔵碑を支える台石が、現在も境内で存在感を放つ大亀像です。
古代中国の思想では「亀趺碑(きふひ)」と呼ばれ、本来は「亀」ではなく「龍」を象ったものとされています。
しかしその姿から、人々の間では「化け亀」とも呼ばれ、明治の文豪・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の著作にも登場しました。
こうした物語性と文学的背景をもつ大亀像は、長寿祈願の象徴であると同時に、松江の文化を語るうえで欠かせない存在です。
さらに2025年には、小泉八雲の妻・セツをヒロインとしたNHKの朝の連続テレビ小説をきっかけに、改めて注目を集めています。
長い歴史を背負いながら、今も人々の祈りと文化を結び続ける――大亀像は、まさに月照寺を象徴する存在です。
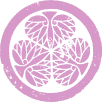
長寿祈願の象徴として

松平家七代治郷公(不昧公)が、
父・宗衍公の徳を讃え、
長寿を祈願するために建立した寿蔵碑。
その台石として据えられた大亀像は、
以来「長寿の象徴」として
人々に親しまれてきました。
やがて、この亀にあやかって自らや
家族の健康長寿を祈る人が訪れるようになり、
現在も境内を訪れる多くの参拝者が
願いを込めて手を合わせています。

お参りの際には、合掌して一礼し、
大亀像の頭をやさしく撫でて
長寿を願うのが習わしです。
大亀像は、長寿祈願の象徴であると同時に、
訪れる人々の未来を見守る存在となっています。

伝承と小泉八雲の物語
松江藩主・松平家の史跡、
月照寺に佇む大亀像には、
長寿祈願の象徴であると同時に、
不思議な怪談としての一面もあります。
明治の文豪・小泉八雲は
『知られざる日本の面影』の中で、
この「化け亀」と呼ばれる存在を紹介し、
月照寺の奇妙な伝承を広く知らしめました。

八雲の著作に登場する「化け亀」の伝承によれば、この大亀像は夜な夜な動き出し、人々に災いをもたらす恐ろしい存在だったと語られています。
村人たちは恐れて手を付けられず、ついには寺の住職が仏の教えを説き、亀に懺悔を促しました。
すると亀は、「自分の力ではどうにもならない」と答え、最後には自ら大きな石碑を背負い、二度と動けぬよう自らを封じたと伝えられています。
その姿こそが、今も境内に残る寿蔵碑を背負う大亀像であり、伝説と実物が重なり合った存在なのです。
八雲はこの怪異譚を紹介することで、大亀像を単なる石造物ではなく、「動かぬことで人々を守る守護の象徴」として描き出しました。
こうして文学の中で物語化されたことで、大亀像は松江を代表する伝承のひとつとなり、今も語り継がれています。
この語りは、文学的な言葉を通じて、石像がただの祈念物ではなく、語り継ぐべき伝説として人々の心に残る理由の一つになっています。
そして2025年、八雲の妻・セツがNHKの朝ドラの主人公に選ばれたことにより、大亀像は新たな注目を浴びています。